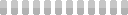伝統的工芸品萩焼専門窯元陶房大桂庵樋口窯のプロフィール
【萩焼伝統工芸士・樋口大桂について】
「萩焼との出会い・萩焼の特徴と作陶への思い」
樋口大桂は東京に生まれ育ち、高校時代に観た三輪休和氏の白釉の抹茶碗に魅了され、1975年に東京から山口県萩市に移り住みました。
市内の窯元で10年間の修行を積み、1985年に手作りによるこだわりの萩焼窯元として開窯し、1991年にお客様に自分で説明し直接お渡ししたいという思いから、松下村塾から徒歩3分の地に「陶房大桂庵樋口窯」を開店しました。
萩焼は2002年に経済産業省から「伝統的工芸品」に指定され、樋口大桂は2004年より伝統的工芸品公募展に出品し入選歴を重ね、2013年萩焼伝統工芸士会が設立されたことにより認定試験を受け萩焼伝統工芸士に認定され、伝統的工芸品萩焼の専門窯元として樋口大桂の三大基本理念のもとに丁寧に作った和食器・花器・茶道具・置物などを作っております。
「樋口大桂の考える萩焼」
陶土(大道土と赤土)・化粧掛けの有無・釉薬(木灰釉・わら灰釉・鉄釉)・焼成(酸化・還元)により表現されるやきものであり、人工的な釉薬や着色料による色付けはしない
「樋口大桂の三大理念」
・粘土から作った陶器ならではの「土のぬくもり」が伝わること
・国産の天然原材料・手作り・高温焼成(1280~1300℃)により「高品質」であること
・コーティング剤不使用(花器以外)により「安心・安全仕様」であること
「萩焼の特徴-萩の七化け」
萩焼は伝統的工芸品萩焼の指定材料である「大道土」を主に使いますが、この陶土が焼き締まらないという特性がある為、生地で素焼きし釉薬を掛けて本焼きをするという工程で作ります。焼成後、生地と釉薬の収縮率の違いにより貫入(かんにゅう)が起こります。器に色見のある水分を入れると、この貫入に染みご使用の度合いによって風合いが変化していくことを「萩の七化け」と言われ、作り手が作ったやきものを使い手が育てていくと言われる所以です。
私どもはこの特徴を尊重し時流に流されることなく伝統的な萩焼を守りたいという精神と、お客様のことを大事にしたいという想いから、器へのコーティングをしないという方針を貫いておりますので、電子レンジ・食器洗浄乾燥機をお使いいただけます。日々の暮らしの中で、萩焼の特徴をお楽しみいただきつつ安心・安全にお使いいただければ幸いです。
「樋口大桂の陶歴」
所属 ・日本工芸会山口支部・萩陶芸家協会理事・萩焼伝統工芸士会監査
1973年 東京デザイナー学院工業工芸科で陶芸の基礎を学び、以降、 萩の窯元で修業
1977年 第26回萩市美術展入選【壷】
1985年 萩で独立・薪窯(単窯)築窯・ガス窯築窯
1990年 第44回山口美術展入選-鬼萩茶碗
1991年 店舗「陶房大桂庵樋口窯」開店
1992年 第89回九州・山口陶磁展入選-萩化粧線紋壷
1992年 第10回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」入選-萩井戸形茶碗
1993年 第30回九州・山口陶磁展入選-萩化粧線紋八角壷
1995年 電気窯築窯
1996年 第93回九州・山口陶磁展入選-結晶釉輪花二重口壷
1996年 第1回アジア工芸展入選-陶花結晶吹雪
1996年 第34回朝日陶芸展入選-結晶釉輪花組鉢
1996年 横浜・高島屋「樋口大桂作陶展」開催
1997年 第14回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」入選-彩釉六角水指
2000年 第35回西部工芸展入選-萩化粧掛分壷
2000年 横浜・高島屋「萩作陶二十五年樋口大桂展」開催
2002年 第49回日本伝統工芸展入選-萩緋色掛分壷
2002年 日本橋三越本店「萩陶芸家協会選抜展」出品
2003年 日本工芸会山口支部伝統工芸新作展支部長賞受賞-化粧掛分窯変花器
2004年 第29回日本伝統的工芸品公募展入選-鬼白丸組皿
2005年 鬼白綴目組鉢で入選
2006年 緑星釉木の葉組鉢で入選
2007年 掛分け丸平鉢で入選
2008年 萩掛分け組鉢で入選
2009年 萩掛分け七角鉢揃で入選
2010年 鉢鉄赤釉末広で入選
2011年 組皿黒釉藁流し丸で入選
2012年 茶器鬼白丸鉄砲口汲出し朝顔で入選
2013年 萩焼伝統工芸士認定される
2013年 青釉酒器&カップで入選
2014年 鉄釉抹茶碗で入選
2017年 彩季豆小鉢で入選
「萩焼との出会い・萩焼の特徴と作陶への思い」
樋口大桂は東京に生まれ育ち、高校時代に観た三輪休和氏の白釉の抹茶碗に魅了され、1975年に東京から山口県萩市に移り住みました。
市内の窯元で10年間の修行を積み、1985年に手作りによるこだわりの萩焼窯元として開窯し、1991年にお客様に自分で説明し直接お渡ししたいという思いから、松下村塾から徒歩3分の地に「陶房大桂庵樋口窯」を開店しました。
萩焼は2002年に経済産業省から「伝統的工芸品」に指定され、樋口大桂は2004年より伝統的工芸品公募展に出品し入選歴を重ね、2013年萩焼伝統工芸士会が設立されたことにより認定試験を受け萩焼伝統工芸士に認定され、伝統的工芸品萩焼の専門窯元として樋口大桂の三大基本理念のもとに丁寧に作った和食器・花器・茶道具・置物などを作っております。
「樋口大桂の考える萩焼」
陶土(大道土と赤土)・化粧掛けの有無・釉薬(木灰釉・わら灰釉・鉄釉)・焼成(酸化・還元)により表現されるやきものであり、人工的な釉薬や着色料による色付けはしない
「樋口大桂の三大理念」
・粘土から作った陶器ならではの「土のぬくもり」が伝わること
・国産の天然原材料・手作り・高温焼成(1280~1300℃)により「高品質」であること
・コーティング剤不使用(花器以外)により「安心・安全仕様」であること
「萩焼の特徴-萩の七化け」
萩焼は伝統的工芸品萩焼の指定材料である「大道土」を主に使いますが、この陶土が焼き締まらないという特性がある為、生地で素焼きし釉薬を掛けて本焼きをするという工程で作ります。焼成後、生地と釉薬の収縮率の違いにより貫入(かんにゅう)が起こります。器に色見のある水分を入れると、この貫入に染みご使用の度合いによって風合いが変化していくことを「萩の七化け」と言われ、作り手が作ったやきものを使い手が育てていくと言われる所以です。
私どもはこの特徴を尊重し時流に流されることなく伝統的な萩焼を守りたいという精神と、お客様のことを大事にしたいという想いから、器へのコーティングをしないという方針を貫いておりますので、電子レンジ・食器洗浄乾燥機をお使いいただけます。日々の暮らしの中で、萩焼の特徴をお楽しみいただきつつ安心・安全にお使いいただければ幸いです。
「樋口大桂の陶歴」
所属 ・日本工芸会山口支部・萩陶芸家協会理事・萩焼伝統工芸士会監査
1973年 東京デザイナー学院工業工芸科で陶芸の基礎を学び、以降、 萩の窯元で修業
1977年 第26回萩市美術展入選【壷】
1985年 萩で独立・薪窯(単窯)築窯・ガス窯築窯
1990年 第44回山口美術展入選-鬼萩茶碗
1991年 店舗「陶房大桂庵樋口窯」開店
1992年 第89回九州・山口陶磁展入選-萩化粧線紋壷
1992年 第10回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」入選-萩井戸形茶碗
1993年 第30回九州・山口陶磁展入選-萩化粧線紋八角壷
1995年 電気窯築窯
1996年 第93回九州・山口陶磁展入選-結晶釉輪花二重口壷
1996年 第1回アジア工芸展入選-陶花結晶吹雪
1996年 第34回朝日陶芸展入選-結晶釉輪花組鉢
1996年 横浜・高島屋「樋口大桂作陶展」開催
1997年 第14回田部美術館大賞「茶の湯の造形展」入選-彩釉六角水指
2000年 第35回西部工芸展入選-萩化粧掛分壷
2000年 横浜・高島屋「萩作陶二十五年樋口大桂展」開催
2002年 第49回日本伝統工芸展入選-萩緋色掛分壷
2002年 日本橋三越本店「萩陶芸家協会選抜展」出品
2003年 日本工芸会山口支部伝統工芸新作展支部長賞受賞-化粧掛分窯変花器
2004年 第29回日本伝統的工芸品公募展入選-鬼白丸組皿
2005年 鬼白綴目組鉢で入選
2006年 緑星釉木の葉組鉢で入選
2007年 掛分け丸平鉢で入選
2008年 萩掛分け組鉢で入選
2009年 萩掛分け七角鉢揃で入選
2010年 鉢鉄赤釉末広で入選
2011年 組皿黒釉藁流し丸で入選
2012年 茶器鬼白丸鉄砲口汲出し朝顔で入選
2013年 萩焼伝統工芸士認定される
2013年 青釉酒器&カップで入選
2014年 鉄釉抹茶碗で入選
2017年 彩季豆小鉢で入選